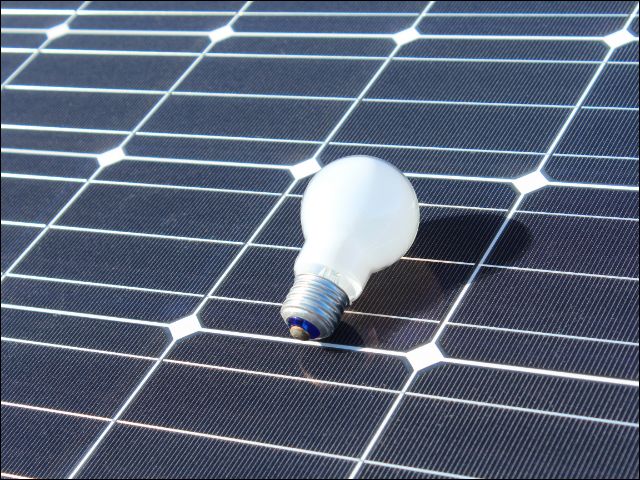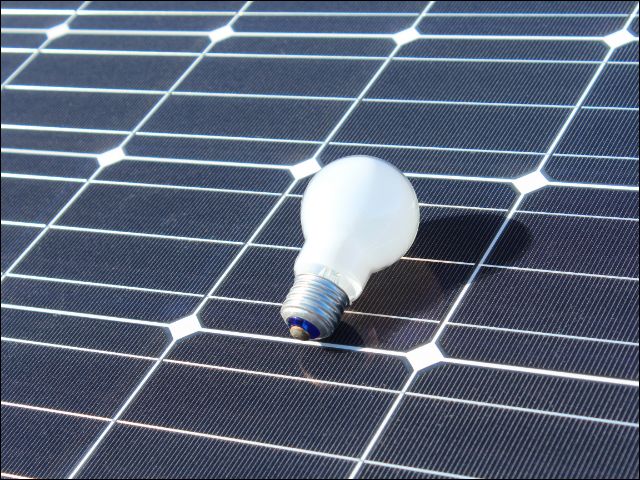「系統用蓄電池」という存在をご存じでしょうか? 太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーの普及で蓄電池の存在は多くの人が知ることになったかと思いますが、そのような一般的な蓄電池と違い、「系統用蓄電池」の存在やその性質は意外と知られていないかもしれません。
実は、系統用蓄電池は単なる電力貯蔵装置ではなく、電力市場での取引を通じて収益を生み出すビジネスツールとしての側面も持っています。卸電力市場、需給調整市場、容量市場という3つの市場で、それぞれ異なる方法で収益化を図ることが可能です。
太陽光発電の普及により電力需給の変動が大きくなる中、この変動を調整し収益に変える系統用蓄電池のビジネスモデルについて詳しく見てみます。
系統用蓄電池とは?
系統用蓄電池について正しく理解するために、まずその基本的な仕組みと、なぜ今注目されているのかを確認しましょう。
系統用蓄電池の仕組み
まず、発電した電気を各地へ送るための送電網や配電網のことを「電力系統」と呼びます。一般的な家庭用の蓄電池や産業用蓄電池はこの電力系統とは切り離され、主に昼間の発電で余った電力を夜間に使用するように使われたり、万が一の災害などで停電になった場合の非常用電源として利用されたりします。
一方で、電力系統に直接接続して充電と放電を行う大型蓄電池を「系統用蓄電池」と呼びます。最も重要な特徴は、電力系統とリアルタイムで連携し、電力の需給バランス調整を行うことです。電力の需要が多い時には放電して電力を供給し、需要が少ない時には充電して余剰電力を貯蔵します。
また、系統用蓄電池は高速応答が可能で、数秒から数分という短時間で充放電の切り替えができます。この特性により、電力系統の瞬時的な変動にも対応し、系統全体の安定性を維持する役割を果たしています。
系統用蓄電池が必要とされる理由
系統用蓄電池の需要が急拡大している背景には、再生可能エネルギーの大量導入があります。特に太陽光発電は天候により発電量が大きく変動するため、電力系統にとって不安定要素となります。
従来の電力系統は、火力発電などの調整可能な電源により需給バランスを保ってきました。しかし、太陽光発電の普及により、昼間の余剰電力と夕方の電力不足という課題が発生しています。
系統用蓄電池は、この需給の時間的なズレを調整する役割を担います。昼間の余剰電力を蓄電し、夕方から夜間にかけて放電することで、電力系統の安定化に貢献します。
また、電力の需給バランスが崩れると停電のリスクが高まりますが、系統用蓄電池の高速応答により、このようなリスクを大幅に低減できます。電力の安定供給という社会インフラの観点からも、系統用蓄電池の重要性は高まっています。
系統用蓄電池のビジネスモデル
系統用蓄電池は、複数の電力市場での取引を通じて収益を生み出します。それぞれの市場での収益化メカニズムを詳しく見てみましょう。
収益化方法①:卸電力市場にて売買(アービトラージ)
卸電力市場でのアービトラージは、電力価格の時間差を利用して収益を得る手法です。電力価格の安い時間帯に充電し、価格の高い時間帯に放電することで、価格差から利益を生み出します。
日本卸電力取引所(JEPX)では、30分ごとに電力価格が決定されます。例えば、太陽光の発電量が増える晴れた日の昼間などの電気の余る時間帯は安く電気を購入することができ、夕方などの発電量が減少して電力需要が増加する時間帯は高く電気を売ることができます。この価格差は時期により異なりますが、5~20円/kWh程度の差が生じることもあります。
例えば、5円/kWhで電気を購入して充電し、需要が高まった時間帯で25円/kWhで売電した場合、1kWhあたり20円の粗利益を得ることができます。100MWhの容量の蓄電池であれば、1回の充放電サイクルで最大200万円の収益が期待できる計算になります。
ただし、実際の収益は市場価格の変動や充放電効率、運用コストなどを考慮する必要があります。また、価格予測の精度が収益性に大きく影響するため、高度な市場分析技術が求められます。
収益化方法②:需給調整市場
需給調整市場は、電力の需給バランスを維持するためのサービスを提供する市場です。系統用蓄電池は、その高速応答性を活かして、需給調整サービスを提供し対価を得ることができます。
需給調整市場には、「一次調整力」「二次調整力①」「二次調整力②」「三次調整力①」「三次調整力②」という5つの区分があります。蓄電池は特に、秒単位での高速応答が求められる一次調整力と二次調整力①での活用が期待されています。
収益は「容量確保対価」と「電力量対価」の2つから構成されます。容量確保対価は、調整力を提供する能力を確保することに対する対価で、電力量対価は実際に調整力を発動した際の対価です。
一般的に、一次調整力の容量確保対価は月額で数千円/kW、二次調整力①では月額で数百円から数千円/kW程度とされています。100MWの蓄電池システムの場合、月額で数千万円から数億円規模の収益が期待できます。
収益化方法③:容量市場
容量市場は、将来の電力供給能力を確保するための市場で、2024年度から運用が開始されました。系統用蓄電池も、一定の条件を満たせば容量市場への参加が可能です。
容量市場では、4年後の電力供給能力に対して「容量確保契約」を締結し、その対価として「容量収入」を得ることができます。この仕組みにより、電力設備への投資回収の予見性が向上し、長期的な事業計画の策定が可能になります。
2024年度の約定価格は年額で14,137円/kWとなっており、100MWの蓄電池システムの場合、年間約14億円の容量収入が期待できる計算になります。ただし、実際の供給力として認められるためには、技術的な要件や運用実績の証明が必要です。
容量市場での収益は長期間にわたって安定しているため、系統用蓄電池の投資回収計算において重要な収益源となります。また、他の市場での収益と組み合わせることで、より安定したビジネスモデルを構築できます。
多面的な収益モデルの構築
系統用蓄電池のビジネスモデルは、単一の収益源に依存するのではなく、複数の電力市場を活用した多面的な収益構造が特徴です。卸電力市場でのアービトラージ、需給調整市場での調整力提供、容量市場での容量確保という3つの収益源を組み合わせることで、リスクを分散しながら安定した収益を確保できます。
電力市場の制度整備が進む中、系統用蓄電池の価値はますます高まっています。太陽光発電の普及により電力需給の変動が大きくなる現在、この変動を収益機会に変える系統用蓄電池への注目は今後も続くでしょう。
ただし、電力市場での取引には専門的な知識と経験が必要であり、市場動向の分析や運用戦略の策定が成功の鍵となります。